スーツ?私服?インターンシップや面接の服装はどうすればいいの?
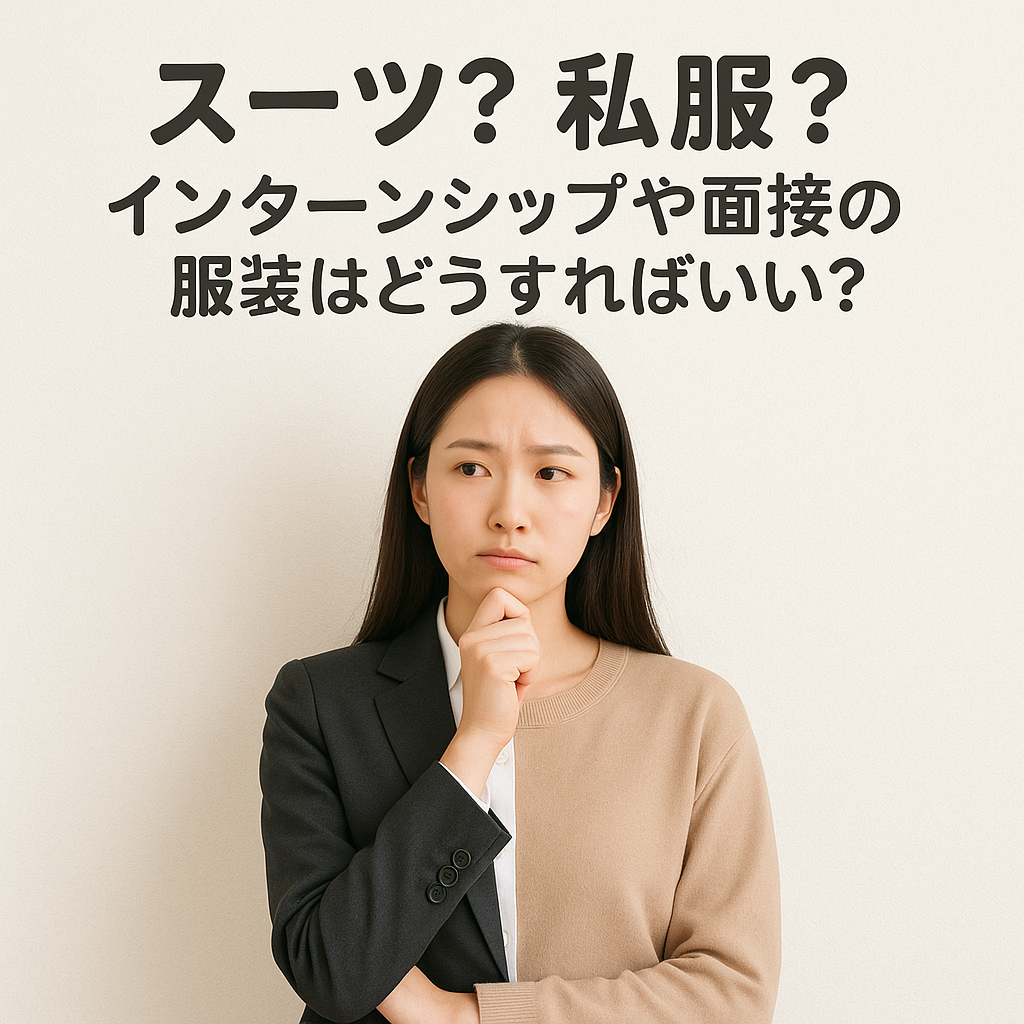
よくある質問:「面接の服装ってどうしたらいいですか?」
インターンシップの対面面接を行う前に、応募者の方とはメールでやり取りをさせていただきます。
(海外在住の方や事情がある場合は、LINE WORKSなどのチャットツールを使うこともあります。)
そのやり取りの中で、よくいただくのがこんな質問です。
- 面接の際の服装はどうしたら良いでしょうか?
- 面談当日はスーツで行った方がいいでしょうか?
うんうん、分かります。不安になりますよね。
特に大学生にとっては、毎日スーツを着ているわけではないですし、大学の授業帰りにそのまま来ることもあるでしょうから。
服装に「正解」はあるのか?
実は、面接の服装について私たちから一律の指示はしていません。
応募者の皆さん自身に考えてもらうことを大切にしているからです。
インターンシップはアルバイトとは違います。
応募した瞬間から、すでに“社会人としての学び”は始まっています。
だからこそ、「この場にどんな服装で臨むべきか」を自分で考えることが、最初のビジネスマナーの一歩になるのです。
ビジネスにおける服装=「相手への配慮」
文部科学省はインターンシップを「学生が在学中に、専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」、
厚生労働省は「学生が企業で実際に働くことで、働くことへの理解を深め、自らの適性や職業能力の向上を図ること」
と定義しています。
つまり、インターンとは「社会人として振る舞う練習の場」です。
では、ビジネスにおける服装の正解とは何でしょうか。
正直に言えば、絶対の正解はありません。
ただし一つだけ確かなのは、服装とは「自分をどう見せたいか」だけではなく、相手が不快に思わないかどうかという視点が大切だということです。
清潔感があること。場の雰囲気を壊さないこと。
これこそが、最低限の“ビジネスにおける身だしなみ”だと考えています。
服装は自由。でも「自由=なんでもいい」ではない
私自身、高校時代は制服がなく私服通学でした。
その自由な校風のおかげで「見た目だけで人を判断するのは難しい」ということや、逆に「どう見られているかが大切だ」ということを実体験として学びました。
髪を茶色にしていた時期もあり、部活の試合に行くと浮いて見えたり、「悪そう」と思われたり(笑)。
そういう経験から、「自由には責任が伴う」「メリハリが大事」ということを強く意識するようになりました。
だからこそ、大阪中央会計のインターンでも、服装の自由を認めつつ、それを考えるきっかけにしてほしいと思っています。
「今日はスーツで行こう」
「今日はジャケットにシャツで十分だろう」
――その選択に自分なりの理由を持てるかどうか。
それが、社会人に必要な感覚だと思うのです。
まとめ:服装は「学びのきっかけ」
結論を言うと、インターンの面接や参加時の服装に唯一の正解はありません。
ですが、自由だからこそ「どう見られるか」を考え、相手への配慮を忘れないことが大切です。
大阪中央会計のインターンは、服装一つとっても学びのきっかけにしてほしいと願っています。
「なんでもかんでも指示される」のではなく、「自分で考えて選ぶ」。
その積み重ねが、AIやマニュアルでは代替できない“人間らしい力”につながるはずです。
